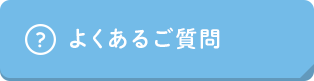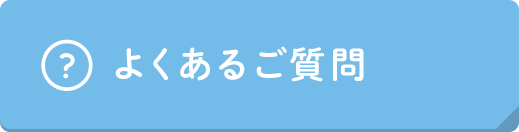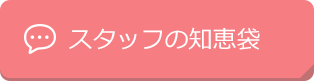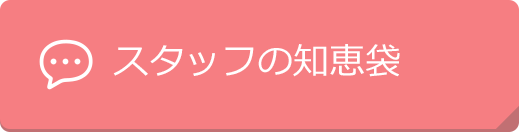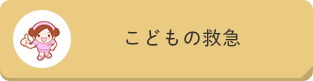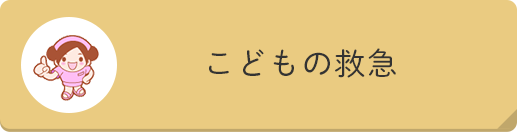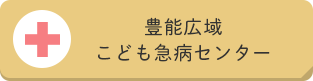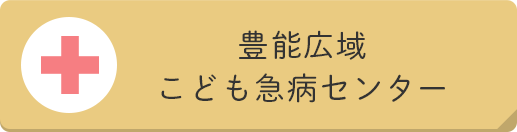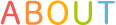2015.04.30更新
虚弱、という考え方について
ただでさえ、苦い薬が苦手なこども達に、漢方の独特な臭いの強い煎じ薬を処方するのは、漢方好きな院長としても、かなり気が引けるところではあるのですが、西洋の薬にはない、虚弱児の生活改善、という非常に魅力的な面があり、時々提案させてもらっています。
代表的な薬が、小建中湯。お腹が冷え気味だったり、食欲が細かったり、便秘だったり、お腹の関する子供の問題には良く出る薬です。病気とも言えないけど、お母さんとしては、もうちょっと食べて欲しいとか、線が細くて便秘しがちの子供さんにはうってつけ。
食欲を増やす漢方には、六君子湯というのもあります。なんかの拍子に吐きやすく、食欲も日頃からいまいち・・・なんてお子さんには良いでしょう。
ほかにもいろんな病気とも言えない症状に対して、お出しできる薬があります。
が・・・
やっぱり飲ませずらいんですよね。結局、飲めば効く!という信念と、親御さんのがんばり、かなりの覚悟が必要になってきます。(これは抗菌薬でもおなじで、苦い薬を飲ませる覚悟は必要です。)
そこで、漢方の場合、こんな飲ませ方をお勧めしています。
水飴、はちみつ(1歳以上)に混ぜる。1歳未満のお子さんにはマルツエキスという麦芽糖のお薬に混ぜてもらうこともあります。
2,3歳以上のお子さんであれば、1回お湯に溶いて、冷蔵庫で冷やし、100%リンゴジュースで割って飲むなど。
甘いのが苦手なお子さんは、濃い目のお茶、麦茶で割るとよいみたいです。
漢方が飲みやすく感じる場合、体質と合っている可能性が高く、効果がより出やすいと言えるでしょう。
漢方トライしてみたい方、ご相談ください。
ちなみに普通の風邪、嘔吐、下痢、アトピーなど、西洋の薬より効く漢方も多くあります。西洋の薬飲んでみたけど、いまいち効かない、なんて場合でもOKです。
投稿者:
2015.04.29更新
3歳~学童の予防接種
春から入園・入学した子も、転居で新生活を始めた親御さんたちも環境に少しずつなれてきた頃でしょうか
赤ちゃんの時は母子手帳を見る機会が多く、また健診や受診の機会も多いため、見逃すことが少ない予防接種ですが、3歳頃になるとめっきり見なくなる母子手帳...。
そこで、今回は3歳頃~学童期に接種する予防接種についておさらいしておきましょう
日本脳炎に関しては生後半年~接種可能ですが、標準接種期間は3歳からなので記載しておきます。
3歳: 日本脳炎(1期1回目・2回目)
4歳: 日本脳炎(1期追加)
年長(5-6歳): 麻疹風疹2期・おたふくかぜ2回目
9歳~13歳未満: 日本脳炎2期
11歳~13歳未満: 二種混合
平成7~18年度に生まれた方は日本脳炎の予防接種を控えていた時期に該当するため、受ける機会を逃していることがあります。接種については厚生労働省や市町村のHPより情報を確認いただくとともに、一度ご相談ください。
久しぶりに
母子手帳を見てみませんか?
看護スタッフ
投稿者:
2015.04.28更新
バイオリンとピアノ
日曜日に直原ウィメンズクリニックでピアノとバイオリンの演奏会がありました。無料で聞ける演奏会としてはハイレベル(私は音痴なので、わからないですが、奥さんによると上手だった!とのこと)。
こども達も多く、なかなか騒がしかったものの、生の楽器の音のシャワーを浴び、非常に心地よい空間でした。子連れだとなかなかいけないので、すごく貴重な体験。感謝です。
さて、そんな中、うちの子供はすごく楽しみにして、朝から盛り上がり、疲れ果て、午後2時に、僕の膝の上、クラシックを聴きつつ、という環境もまずかったのか、2曲目で速攻寝付いてしまいました。モッタイナイ・・・
そんな彼、最後の曲が終わると、ぱっと目覚め、楽しかった!と^^;
うーむ、どんな夢を見ていたのやら。。。
投稿者:
2015.04.24更新
ヒルドイドとビーソフテンについて
さて、当院ではプロペトの他に、保湿剤でどっちかが出ることが多いです。どちらかをもらった、という患者さんが多いのではないでしょうか。
では、どういう違いがあるか、ご存じですか?ビーソフテンは後発品なので、本来、ヒルドイドとおなじ薬効を持っているのですが、それは含まれているヘパリン類似物質に限ってのこと。他の基剤については、微妙な違いがあるんです。
ということで、それぞれの成分表を見てみました。ほとんどの成分表は多い順に並んでいると思っていますが、グリセリンが基剤になっているようですね。その次にスクワラン!?
うーむ。意外ですね。お母さんたち女性には、化粧品などでなじみのある響きのはず。
ちなみにビーソフテンローション、スプレーにスクワランは入っていないようです。
塗り心地の比較をすると、ヒルドイドソフトは若干硬く、塗りにくいが、塗った後のべたつきは少なめ。ビーソフテン油性クリームは伸びが良いが、油でべたべたになる。
ヒルドイドローションは伸びもよく、塗り心地が良いです。ビーソフテンローションは本当に化粧水レベルのさらさら感。保湿というより、化粧水。本当に暑い夏には良いかも。
というわけで、私なりの使いわけ。
ヒルドイドソフト:がさがさ、アトピー肌には最適。幼児向け。
ビーソフテン油性クリーム:乾燥が強い子で多少べたべたでも気にしない、1歳未満、体幹向け。顔には向かない。
ヒルドイドローション:万能。油成分が少ないため、夏向け。化粧のローション代わりにも最強だが。
ビーソフテンローション:日頃、管理が良く、つるつるのお肌の方に。特に夏。
投稿者:
2015.04.11更新
夜泣き
こんにちは、院長です。
生後10カ月頃にやる後期健診で一番多い悩み事が、夜泣きです。お母さんたちも疲れてしまっているのがよくわかります。
まぁ、うちもそうでしたし、過ぎてみるとのど元過ぎて熱さをを忘れ、元気に過ごしています。なので、今だけのことだし、様子を見てれば治るよと言われることが多いのではないでしょうか。
でも、それじゃあまりにもきついですよね。
「夜泣き」を分類して考えてみました。(自己流)
その1:とにかく寝付きが悪く、置くと泣く。おっぱい吸わせていると落ち着いているが、そのうちぐずぐずしてしまう。
その2:夜、頻回に目覚めてしまい、毎回泣いて、おっぱいを欲しがる。
その3:起きるのは2,3回だが、一度起きると1,2時間泣き続ける。おっぱいで落ち着くこともあるが、無理なことが多い。
そのほかにもあるかもしれませんが、大体このようなケースが多いですね。
うちは、その1とその3の合わせ技でした。
その1とかは寝るのが怖いのかな?というケース。
その2は不安が強く、おっぱいへの依存が強いケース。
その3は疳が強く、不安もありそうなケース。
ちなみに1歳以降の夜泣きはまた別の話なので、別の回で書きますね。
この全てに共通するポイントが、寝かしつけにだっこや母乳に頼っていることです。
新生児のころ、母乳は欲しがるだけあげてくださいと言われ、それ以来、赤ちゃん達はお母さんの腕の中で気持ちよく眠りにつくことが多かったと思います。
それが、8ヶ月-10カ月ごろになってくると、様々なことがわかり始め、興奮し、目新しいことやびっくりすることもあり、不安や好奇心が渦巻きはじめます。人見知りが始まるのもこの頃ですよね。その結果、お母さんへの依存が強くなり、より安心感を得ようとします。
そんな中で、今までは多少夜目が覚めてもそのまま眠れていた赤ちゃんたちも、お母さんにだっこされていないこと、おっぱいをくわえていないことに、びっくりし、不安になり、泣いてしまうんですね。
「夜泣き」の始まりです。
では、どうしていくべきか。
おそらく、これ!といった正解はないでしょうが、私の答えを書いておきます。あくまでうちのケースなので、参考にされるかどうかは別としてください。
まず、入眠儀式を大切にします。
部屋を暗くするとか、お気に入りのタオルを作ってやるとか。
ちなみにうちの子は、毛羽だったひもを耳に入れてこちょこちょしてやると、3分後には寝てくれるという不思議なスイッチがあることが判明し、随分楽になりました。
次に、おっぱいへの依存を減らしていきます。(たぶん一番重要)
眠ってしまうまでおっぱいを吸い続けていないように、眠ってしまいそうだな~というときにおっぱいを口から離してやり、泣き始めて目が覚めてしまったら、もう一度おっぱいをくわえさせます。それを繰り返してやるといつかあきらめて寝るようになってくれます。うちの場合、寝る時のおっぱいへの依存をなくすために1ヶ月近くかかりました。
おっぱいなしで腕の中で寝るようになったら、次は、眠ってしまうまえに布団に置きます。これも一緒で、泣いたら、まただっこしてやり、寝る直前に置く練習を繰り返します。するとそのうち、眠くなったら布団に入り、自分で眠る、という習慣が身についていきます。
これがうまくいくようになると、夜目が覚めても自分で寝てくれるようになっていくはずです。
さて、長くなってしまいましたが、以上の方法を試してみても、無理な場合、特に泣き出したら一気にギャン泣きまでいき、手に負えない、と言うような状態であれば、漢方を併用するのも手です。
不安が強かったりすれば、甘麦大棗湯、疳の虫のような、疳が強いのであれば、抑肝散がお勧めです(いずれも処方薬です)抑肝散はお母さんがいらいらしてしまっているようなら、お母さんにも飲んでもらうと効果があります。
なかなかうまくいかない、疲れた!と言うお母さん。一度かかりつけにご相談くださいね。
投稿者:
2015.04.11更新
おならの語源
娘が突然、
「おかーさん、おならは何で〝おなら〟って言うの?」
と言うので
辞書があるんだから調べてみたら?と返し仕事に向かいました。
が・・・気になるので私も調べてみました。
おならとは
「鳴らす」の連用形を名詞化した「鳴らし」に、接続後の「お」がついた
「お鳴らし」を最後まで言わず、婉曲に表現したもので、元女房詞である。
おならは屁を放つときに音が発するものを指すことが多いのに対し、
屁は「すかし屁(すかしっぺ)」などのように、音をださないものを指す。
だそうです。。。
勉強になったわぁ
帰ったら教えてあげなくちゃ
受付
投稿者:
2015.04.04更新
布団とパジャマの話
うちの子だけ
布団かぶって寝ないらしい。
保育園のお昼寝タイムにみんな布団かぶって寝ているのに、かぶらないらしい。
そこで調べてみました。
〇フー知〇袋でみてみたら、すごい数の質問が出てきました。
うん、他の人もおなじか、じゃぁまぁいいか(笑)
患者さんに聞かれたら、そういうわけにもいかないから、考えてみました。
共通点が一つ。
それは服の着すぎと布団の掛けすぎ。これが全部とは言わないけれど、お母さんたち、みんな冷え症気味だったり、寒がりが多い。まぁ冷えは女性にとって大敵なので、これは正しい。でも、こどもの体温に対して、母の基準で着せてしまうと大概が着せすぎです。
こども達は眠くなると、手足や顔が温かくなってきてじっとり汗をかきますよね。あれは汗をかいて、身体の中の熱を逃がして、体温を下げようとしているのです。深部体温を下げることによって深い眠りに入ります。それなのに毛布を掛けようとしたり、あったかくしてやろうとするのは、こどもにとってはありがた迷惑な話になってしまいます。
というわけで、服は湿気を閉じ込めない、通気性がよく、軽く、手足からの放熱を妨げない、お腹を冷やさない程度に。ナイロン毛布など湿気を閉じ込めてしまうものは避けて、通気の良い軽い毛布などがお勧めです。手足が毛布から出ていても全く問題なし。気になるときは室温と湿度を少し上げてあげましょう。
つまり、服は綿のパジャマ(絹も可)。掛け布団はウール、カシミアなどの毛布がお勧めです。パイル生地などのタオルケットでもよいでしょう。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2023年08月 (2)
- 2023年07月 (1)
- 2023年06月 (2)
- 2023年04月 (3)
- 2023年03月 (3)
- 2023年02月 (2)
- 2022年12月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年09月 (5)
- 2022年08月 (3)
- 2022年07月 (4)
- 2022年06月 (2)
- 2022年05月 (2)
- 2022年04月 (3)
- 2022年03月 (3)
- 2022年02月 (1)
- 2022年01月 (2)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年09月 (3)
- 2021年08月 (2)
- 2021年07月 (2)
- 2021年06月 (2)
- 2021年05月 (1)
- 2021年04月 (3)
- 2021年03月 (1)
- 2021年02月 (2)
- 2021年01月 (2)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (4)
- 2020年09月 (3)
- 2020年08月 (4)
- 2020年07月 (3)
- 2020年06月 (1)
- 2020年04月 (2)
- 2020年03月 (3)
- 2020年02月 (6)
- 2020年01月 (3)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)
- 2019年09月 (5)
- 2019年08月 (3)
- 2019年07月 (5)
- 2019年06月 (3)
- 2019年05月 (3)
- 2019年04月 (4)
- 2019年03月 (6)
- 2019年02月 (5)
- 2019年01月 (3)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (7)
- 2018年10月 (1)
- 2018年09月 (9)
- 2018年08月 (5)
- 2018年07月 (3)
- 2018年06月 (6)
- 2018年05月 (6)
- 2018年04月 (1)
- 2018年03月 (5)
- 2018年02月 (4)
- 2018年01月 (3)
- 2017年12月 (9)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (5)
- 2017年09月 (6)
- 2017年08月 (3)
- 2017年07月 (5)
- 2017年06月 (8)
- 2017年05月 (7)
- 2017年04月 (3)
- 2017年03月 (5)
- 2017年02月 (2)
- 2017年01月 (2)
- 2016年12月 (6)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年09月 (4)
- 2016年08月 (3)
- 2016年06月 (2)
- 2016年05月 (2)
- 2016年04月 (1)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (6)
- 2016年01月 (1)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (5)
- 2015年08月 (4)
- 2015年07月 (3)
- 2015年06月 (5)
- 2015年05月 (6)
- 2015年04月 (8)
- 2015年03月 (9)
- 2015年02月 (9)
CATEGORY
- お知らせ (206)
- 病気やおうちでのケア (18)
- スタッフつれづれ話 (40)
- こころのそうだん (1)
- 院長からのお知らせ (1)